※このページにはアフィリエイトリンクが含まれています。

また確定申告の時期も迫ってきたので、ふるさと納税を上手に活用して税負担を軽減しましょう。
ふるさと納税とは?
ふるさと納税とは、「自分の選んだ自治体へ寄附ができる制度」です。
寄附をすると、そのお礼として地域の特産品などの「返礼品」がもらえ、さらに、寄附した金額のほとんどが所得税と住民税から控除(差し引かれる)されるという仕組みです。
寄付した額のほぼ全額(自己負担2,000円を除く)が、翌年の住民税・所得税から控除される。
基本の流れ
応援したい自治体に寄付申込
自治体から「寄附受領証明書」などが届く
税金控除の手続きをする
ワンストップ特例制度
または確定申告
翌年の税金が寄付額に応じて安くなる
控除の計算(イメージ)
年間の寄付額 − 2,000円 が控除対象。
例:5万円寄付 → 48,000円が翌年の住民税などから差し引かれる。
ただし上限額(年収・家族構成で変動)があるため、上限を超えて寄付すると自己負担が増える。
上限額の目安
共働き(扶養なし)・サラリーマン想定の上限額目安
1人あたりの寄付上限額(目安)
| 年収 | 上限額(概算) |
|---|---|
| 300万円 | 約28,000円 |
| 350万円 | 約35,000円 |
| 400万円 | 約42,000円 |
| 450万円 | 約53,000円 |
| 500万円 | 約61,000円 |
| 600万円 | 約77,000円 |
| 700万円 | 約108,000円 |
| 800万円 | 約130,000円 |
| 900万円 | 約150,000円 |
| 1,000万円 | 約176,000円 |
夫婦での考え方(ポイントまとめ)
• 夫婦それぞれの「控除上限額」を個別に計算する
• 夫の上限 + 妻の上限 = 世帯としての「寄付目安額」になる(便宜上の合算)
• 制度上は合算して控除される仕組みはないため、実際の控除は個人ごとに判定される
手順(簡単)
1. 夫の年収で控除上限の目安を確認する
2. 妻の年収で控除上限の目安を確認する
3. それぞれの上限を合計して世帯の寄付目安とする
例(わかりやすい計算)
• 夫:年収600万円 → 上限 約77,000円
• 妻:年収400万円 → 上限 約42,000円
→ 世帯の寄付目安:約119,000円(合計)
注意点(必ず確認すること)
• 合計額は「目安」であり、制度上は個人ごとに控除判定される
• 配偶者控除・扶養人数・社会保険料・他の所得控除などで上限は変わる
• ワンストップ特例を使う場合は夫婦それぞれで申請書を提出する必要がある
• 正確な上限を知りたい場合はシミュレーターを使うか税理士に相談する
税金控除の手続き(2つの方法)
寄附をしても、自動的に税金が安くなるわけではありません。必ず以下のどちらかの手続きが必要です。
| 手続きの方法 | 対象となる人 | 特徴 |
|---|---|---|
| 確定申告 | 誰もが利用可能(給与所得者以外は原則こちら) | 所得税の還付と、住民税の控除が受けられます。 |
| ワンストップ特例制度 | 以下の2つの条件を満たす給与所得者 | 確定申告が不要になり、すべて住民税からの控除となります。 |
| 1. 1年間の寄附先が5自治体以内であること | ||
| 2. ふるさと納税以外に確定申告をする必要がないこと |

ワンストップ特例制度
ワンストップ特例制度は、給与所得者など確定申告が不要な人が、ふるさと納税の寄附について確定申告をせずに住民税から控除を受けられる仕組みです。寄附ごとに自治体へ「特例申請書」を提出することで、翌年度の住民税から控除が適用されます。
対象者(利用できる人)
• 給与所得者などで、原則として「確定申告をする必要がない人」
• 1年間(1月〜12月)に寄附した自治体数が合計で5自治体以内であること
• 年収や医療費控除、住宅ローン控除などで確定申告が必要な場合は利用不可
• 年収が高額で別途の確定申告扱いになるケースや、特定の控除を受ける人は対象外となる場合がある(不明点は「わからない」と明言します)
利用の流れ(手順)
1. 寄附を行う
• 各自治体の申込ページやポータルで寄附手続きを行う(オンライン・郵送・窓口など)。
2. 特例申請書を入手・記入
• 自治体が用意する「特例申請書」をダウンロードまたは自治体から郵送で受け取る。
3. 必要書類を添付する
• 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)の写しを添付する。添付方法は自治体により異なる(郵送・アップロード可)。
4. 申請書を自治体へ提出
• 寄附した自治体ごとに申請書を提出する(郵送またはオンライン提出)。
5. 提出期限を守る
• その年に行った寄附については「翌年1月10日(必着)」が原則的な提出期限であることが多い。自治体の案内を確認すること。
6. 住民税で控除される
• 提出が受理されれば、翌年度の住民税から控除が行われる(年の途中で寄附した場合、控除の反映時期は自治体や給与支払のタイミングにより異なる)。
必要書類・注意点
必要書類
• ワンストップ特例申請書(各自治体所定様式)
• 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証+健康保険証等。自治体の指定に従う)
重要な注意点
• 寄附先が6自治体以上になると制度適用不可(ただし、同一自治体に複数回寄附しても「1自治体」と数える場合があるため確認が必要)
• ワンストップ特例を利用しても、所得税の還付は受けられない(控除は住民税から行われる)
• 申請書提出期限に遅れるとワンストップ特例は使えず、確定申告で手続きを行う必要がある
• 年末寄附の場合、受領証明書の発行や郵送の遅延で期限に間に合わないことがあるので早めの手続きを推奨
• 寄附した自治体で申請の受理に問題があった場合、控除が受けられないことがある
• 配偶者と合わせた「世帯合算」制度はないため、夫婦それぞれが個別に申請・控除を行う必要がある
申請のメリット・デメリット
メリット
• 確定申告が不要な人にとって手続きが簡単(申請書を送るだけで完了)
• 寄附のたびに還付手続きや確定申告をする手間が省ける
デメリット
• 確定申告が必要な人や寄附先が多い人は使えない
• 手続き期限に厳格で、遅れると確定申告が必要になる
• 所得税の還付を受けたい場合は確定申告を選ぶ必要がある






















![【ふるさと納税】 年内お届け先行予約 最短3営業日以内発送 12月31日まで配送指定OK!ランキング上位常連★【生食 OK】カット生ずわい蟹 内容量 500g〜1kg(総重量 700g〜1.3kg) /1〜5箱 [着日指定可]【甲羅組 海鮮 ズワイガニ お歳暮 お中元 ギフト】](https://i0.wp.com/thumbnail.image.rakuten.co.jp/%400_mall/f182028-tsuruga/cabinet/img/024/024-a020-sku-c_.jpg?resize=128%2C128&ssl=1)































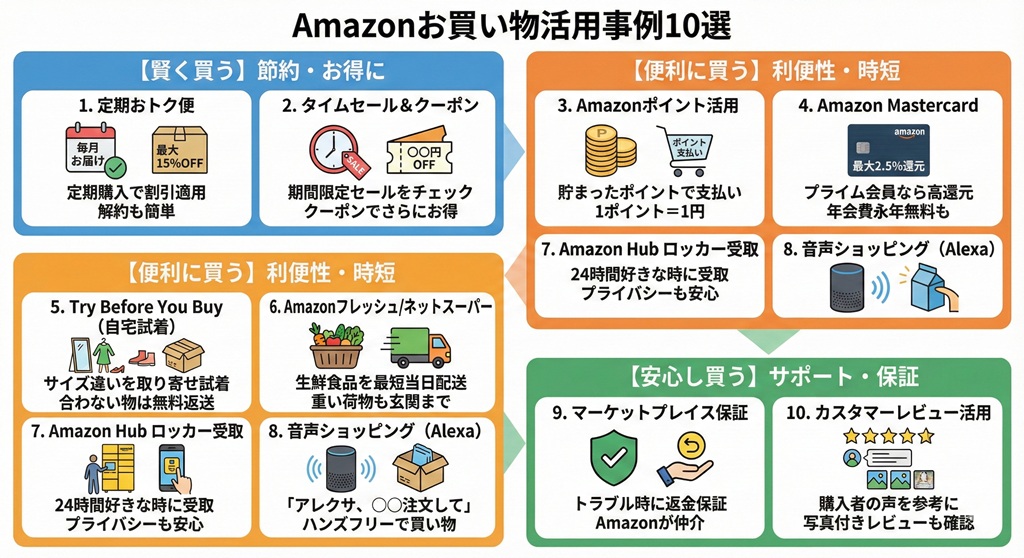


コメント