※このページにはアフィリエイトリンクが含まれています。
🩸 血糖値とは?基本を理解しよう
1. 血糖値の正体
血糖値とは、血液中に含まれるブドウ糖(グルコース)の濃度のことです。ブドウ糖は、私たちが食事から摂取した炭水化物(ご飯、パン、麺、砂糖など)が消化・分解されて作られる、体にとって主要なエネルギー源です。
食後に血糖値が上がると、体はエネルギーとして利用するためにブドウ糖を細胞に取り込もうとします。
2. 血糖値を調節するホルモン
血糖値を一定の範囲内に保つために働く、最も重要なホルモンがインスリンです。
- インスリン(下げるホルモン): 膵臓から分泌され、血液中のブドウ糖を肝臓や筋肉、脂肪細胞に取り込ませて、血糖値を下げます。
- グルカゴン(上げるホルモン): 血糖値が下がりすぎたときに、肝臓に蓄えられたブドウ糖を血液中に放出し、血糖値を上げます。
この二つのホルモンがバランスを取りながら、血糖値はコントロールされています。
📈 血糖値の正常な範囲と異常
血糖値は、測定するタイミングによって基準値が異なります。
| 測定タイミング | 正常値(目安) | 境界型(グレーゾーン) | 異常値(糖尿病の可能性) |
|---|---|---|---|
| 空腹時血糖値(10時間以上絶食) | 100 mg/dL 未満 | 100〜125 mg/dL | 126 mg/dL 以上 |
| 食後2時間血糖値 | 140 mg/dL 未満 | 140〜199 mg/dL | 200 mg/dL 以上 |
| HbA1c(ヘモグロビンA1c) | 5.6 % 未満 | 5.6〜6.4 % | 6.5 % 以上 |
📌 HbA1c とは? 過去1〜2か月の血糖値の平均を反映する指標です。血糖値が高い状態が続くと、血液中のヘモグロビンにブドウ糖が結合した状態(HbA1c)が増えます。
💔 血糖値が高い状態が続くとどうなる?(合併症のリスク)
血糖値が高い状態(高血糖)が続くと、血管がダメージを受け、さまざまな合併症を引き起こします。これが糖尿病です。
特に注意すべきは、糖尿病の三大合併症と呼ばれるものです。
- 網膜症(目): 目の奥にある網膜の血管が傷つき、視力低下や失明に至ることがあります。
- 腎症(腎臓): 腎臓のろ過機能が損なわれ、最終的に人工透析が必要になることがあります。
- 神経障害(神経): 手足のしびれや痛み、感覚の麻痺、自律神経の不調などが起こります。
💪 血糖値を安定させるための具体的な方法
血糖値のコントロールは、主に「食事」「運動」「睡眠」の三つの柱で行います。
1. 🍽️ 食事の工夫
- 食べる順番: 食物繊維が多い野菜・海藻・きのこ類を最初に食べ、次にタンパク質(肉、魚、卵、大豆製品)、最後に炭水化物(ご飯、パン)を食べるのが鉄則です。これにより、ブドウ糖の吸収が緩やかになります。
- GI値の活用: 血糖値の上昇度を示すGI値が低い食品(玄米、全粒粉パン、そばなど)を選ぶと、食後の急激な血糖値の上昇を防げます。
- ゆっくり噛む: よく噛むことで、満腹中枢が刺激され、食べすぎを防ぐことができます。
GI値の意味
• 高GI食品を摂ると血糖値が急上昇 → インスリンが大量に分泌され、脂肪をため込みやすくなる。
• 低GI食品は血糖値の上昇が緩やか → 糖尿病予防、肥満防止、持続的なエネルギー供給に役立つ。
• 食事の組み合わせや調理法によってもGI値は変化します。例えば、同じ米でも「白米>玄米>雑穀米」の順でGI値が低くなります。
GI(グリセミック・インデックス)の基本
• 定義:炭水化物を含む食品を摂取した後、血糖値が上昇する速度と度合いを示す指標。
• 基準:ブドウ糖(グルコース)を GI=100 としたときの相対値で表されます。
• 分類:
• 高GI食品(70以上) → 白米、食パン、じゃがいもなど。血糖値を急激に上げやすい。
• 中GI食品(56〜69) → うどん、パスタなど。
• 低GI食品(55以下) → 玄米、全粒粉パン、豆類、野菜など。血糖値の上昇が緩やか。
2. 🏃 運動の習慣
- 食後の運動: 食後30分~1時間後に、1回15分以上のウォーキングなどの有酸素運動を行うと、血糖値が下がりやすいです。
- 筋力トレーニング: 筋肉はブドウ糖を消費する大きな組織です。スクワットなどの筋トレを組み合わせることで、血糖値が下がりやすい体になります。
3. 🛌 睡眠とストレス管理
- 質の高い睡眠: 睡眠不足になると、血糖値を下げるインスリンの働きが悪くなったり、食欲を増進させるホルモンが増えたりして、血糖値のコントロールが難しくなります。
- ストレス解消: ストレスも血糖値を上げる原因の一つです。リラックスする時間を作り、自律神経のバランスを整えることが大切です。

血糖値を抑える効果が期待される代表的なスーパーフード何?
血糖値を抑える効果が期待される代表的なスーパーフードは、オートミール・チアシード・ナッツ類(特にクルミやアーモンド)・アボカド・玄米などです。これらは低GI食品で、食後の血糖値上昇を緩やかにしてくれます。
🔍 血糖値を抑えるスーパーフードの代表例
1. オートミール(全粒オーツ麦)
• 特徴:水溶性食物繊維「β-グルカン」が豊富。
• 効果:糖の吸収をゆるやかにし、食後血糖値の急上昇を防ぐ。
• 食べ方:朝食に牛乳や豆乳と一緒に、スープやスムージーに加える。
2. チアシード
• 特徴:水分を含むとゼリー状になる。オメガ3脂肪酸も豊富。
• 効果:糖質の吸収を遅らせ、血糖値の上昇を抑える。
• 食べ方:ヨーグルトやスムージーに混ぜる。
3. ナッツ類(クルミ・アーモンド)
• 特徴:良質な脂質とポリフェノールを含む。
• 効果:インスリン感受性を改善し、血糖値の安定に役立つ。
• 摂取目安:1日20〜30g(手のひら一杯程度)。
4. アボカド
• 特徴:食物繊維と良質な脂質を兼ね備えた果物。
• 効果:血糖値の上昇を緩やかにし、満腹感を持続させる。
• 食べ方:サラダ、トースト、ディップソースに。
5. 玄米
• 特徴:白米より食物繊維やビタミンB群が豊富。
• 効果:GI値が低く、血糖値の安定に役立つ。
• 注意点:炊く前に浸水させると消化が良くなる。
✅ まとめ
• 低GI食品(オートミール・玄米・豆類など)は血糖値の急上昇を防ぐ。
• 食物繊維や良質な脂質を含む食品(チアシード・ナッツ・アボカド)はインスリンの働きを助ける。
• 毎日の食事に少しずつ取り入れることで、糖尿病予防や血糖値管理に役立つ。


2025年に人気の血糖値測定器トップ5
1. フリースタイルリブレ
• 特徴:皮膚に貼るセンサーで血糖値を連続測定。
• メリット:針を刺さずに測定でき、スマホでデータ確認可能。
• 人気理由:糖尿病患者だけでなく健康管理目的でも注目されている。
2. テルモ メディセーフフィット血糖測定セット
• 特徴:指先から少量採血して測定。
• メリット:精度が高く、国内での信頼性が厚い。
• 人気理由:医療機関でも採用されることが多い。
3. ワンタッチベリオリフレクト
• 特徴:大画面で見やすく、測定結果を分かりやすく表示。
• メリット:アプリ連携でデータ管理が簡単。
• 人気理由:初心者でも扱いやすい。
4. グルテストアイ(三和化学研究所)
• 特徴:自己検査用のグルコース測定器。
• メリット:シンプル操作で正確な測定。
• 人気理由:国内メーカーの安心感。
5. テルモ メディセーフフィットスマイル
• 特徴:持ち運びやすいコンパクト設計。
• メリット:日常の血糖管理に便利。
• 人気理由:軽量で外出先でも測定可能。
✅ まとめ
• 非侵襲型(刺さないタイプ)では「フリースタイルリブレ3」が圧倒的に人気。
• 採血型では「テルモ メディセーフフィット」シリーズが定番。
• データ管理機能や 使いやすさが選ばれるポイントになっている。
楽天市場の関連商品
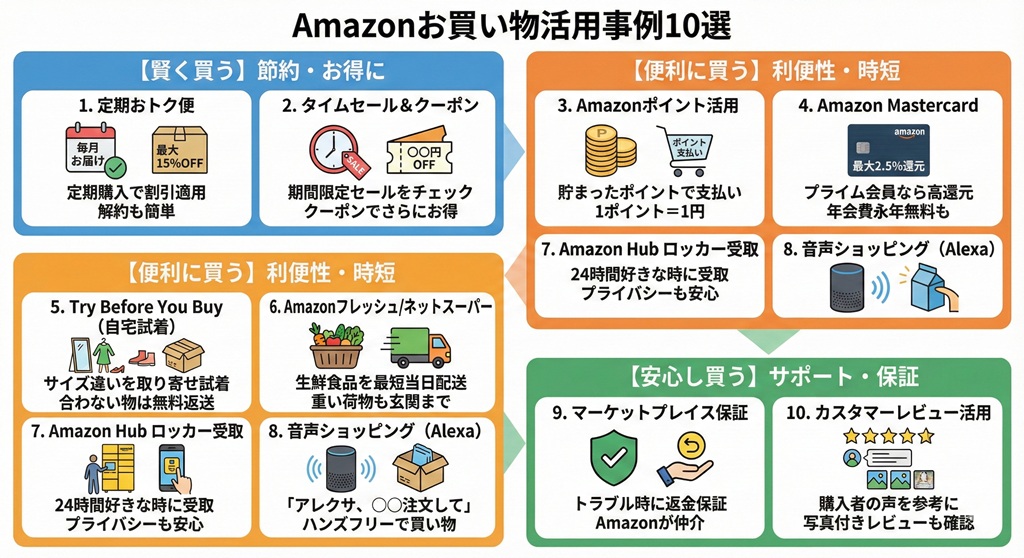








































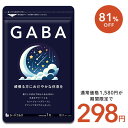


















コメント